演題募集
- 演題登録はUMIN演題登録システムによるインターネットオンライン登録のみです。下段の「登録」ボタンよりご登録下さい。
- 演題登録後も締めきり前であれば抄録等の修正は可能です。登録内容を修正するには、登録時に入力されたパスワード、登録完了後に発行される登録番号が必要となります。セキュリティーの関係から、登録番号とパスワードのお問い合せは一切応じることはできませんので、必ず演題登録時に登録番号とパスワードをお手元にお控え下さい。
- 「必須」の記載がある欄は必須事項ですので、データが入力されていないと登録できません。
演題募集期間
演題募集を終了しました。
応募資格
筆頭著者・共同著者ともに日本肝臓学会員に限ります。
ただし、海外在住の研究者については、理事、評議員若しくは支部評議員の推薦があれば、非会員でも応募できるものとします。
※未入会の方は、至急入会手続きを進めてください。
入会手続きは、「日本肝臓学会ホームページ」をご参照ください。
<入会に関するお問合せ>
一般社団法人日本肝臓学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-10 柏屋2ビル5階
TEL:03-3812-1567 FAX:03-3812-6620
若手セッション
卒後10年以内の若手医師が発表した症例報告の中から優秀演題に 対して、「若手医師症例報告奨励賞」として、 若干名に賞状と奨励金が贈呈されます。今回は筆頭演者が2009 年3月卒業以降の先生を対象としました。
利益相反状態(COI)申告書について
日本肝臓学会は、学会員の利益相反(conflict of interest: COI)状態を公正にマネージメントするために、2011年6月4日(通常総会終了翌日)より「臨床研究の利益相反に関する指針および細則」を試行的に運用し、2013年4月より「医学研究の利益相反に関する指針および細則」を完全実施しました。
2015年3月27日の平成26年度第3回定例理事会において『一般社団法人日本肝臓学会医学研究の利益相反に関する指針』及び『同細則』が承認しました。
本指針は本学会における医学研究の公正・公平さを維持し、学会発表での透明性、社会的信頼性を保持しつつ産学連携による医学研究の適正な推進を図るために、日本内科学会、日本消化器病学会などの関連学会の指針を基盤として策定したものです。この指針の適正かつ円滑な運用のために「医学研究の利益相反に関する指針の細則」に従って申請書の提出をお願いいたします。
今回の改正では、学術集会における演題発表においては、演者全員の申請が必要になりますので、ご注意願います。
※詳細は下記にてご確認ください。
- 医学研究の利益相反に関する指針 一般社団法人日本肝臓学会(315KB)
- 医学研究の利益相反に関する指針細則 一般社団法人日本肝臓学会(312KB)
演者は、配偶者、一親等の親族、生計を共にする者も含めて、今回の演題発表に際して、医学研究に関連する企業や営利を目的とした団体との経済的な関係について過去1年間における利益相反(COI)状態の有無を、抄録登録時に自己申告していただきます。
○抄録登録時申告方法手順
演題応募者は、演題登録の際に、登録ページの「利益相反の自己申告について」にて入力フォームに利益相反の有無を入力してください。また、「筆頭発表者のCOI申告書」をダウンロードして記入のうえ、 FAX、郵送、PDFファイル化してmailのいずれかで演題登録後速やかに提出願います。なお、申告は発表者全員を取りまとめて、当該発表演題に関連した企業との金銭的なCOI状態を記入願います。本COI申告は演題発表後2年間保管されます。不採用の場合は、破棄します。抄録登録時から遡って過去3年間以内のCOI状態を申告して下さい。
<COIに関する発送・ 問合わせ先>
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-10 柏屋2ビル 5階
一般社団法人日本肝臓学会事務局
FAX:03-3812-6620 E-mail:office@jshep.org
○当日発表時開示方法
当日申告すべき利益相反有無に関わらず、状況を開示いただきます(タイトルスライドの後(2枚目))。
○発表当日の開示フォーム
スライド2枚目(タイトルスライドの次)に、様式1-Aまたは1-Bを挿入して開示して下さい。
演題応募上のご注意
人を対象とする臨床研究に関しては、文部科学省、厚生労働省が平成26年12月22日に策定し、平成27年4月1日より実施された「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づくものとされています。以下の点について事前にご手配願います。
URL:http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1443_01.pdf 参照
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」では、全ての研究に倫理委員会の承認を得る必要があります
ただし、侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査、または軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査に関しては、下記のように定められています。
「倫理審査委員会が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行い、意見を述べることができる。迅速審査の結果は倫理審査委員会の意見として取り扱うものとし、当該審査結果は全ての委員に報告されなければならない。」
すなわち、たとえば一人の委員がみて承認し、他の委員に知らせることで倫理審査委員会の承認を得ることができます。貴施設におかれましては、このような体制を早急に整備し、発表までに審査を受けるようにしてください。
募集区分
主題演題
シンポジウム1
| 座長: | 横須賀 收(船橋中央病院) |
| 西口 修平(兵庫医科大学内科学肝胆膵科) |
B型肝炎の抗ウイルス療法は核酸アナログが主流であり、広く使用されている。最近の製剤は耐性変異の危険性は低く副作用も軽減されている。しかし、中止後に高率に再燃することや肝発癌率の低下が十分でないことなどが指摘されている。一方、Peg-IFNはB型慢性肝炎治療の第一選択薬となっているが、有効率が低いことや副作用が多いことなどから使用頻度は低い。近年、Peg-IFNと核酸アナログを併用するsequential治療やadd on療法が工夫されており、その効果が期待されている。
C型肝炎の治療はDAAs製剤の登場によりSVR率は98%近くとなった。しかし、治療抵抗例も少なからず存在しており、DAAs製剤のみでSVR率100%を達成できるのかが一つの課題として残されている。また、HCV陽性にもかかわらず、治療を受けていない患者が多数存在すると予想され、SVRとなっても肝発癌の危険性が残ることと合わせ、C型肝炎治療には課題が残されている。
本シンポジウムでは、B型およびC型肝炎に対する抗ウイルス療法の残された課題を討論する。
シンポジウム2
| 座長: | 池田 健次(虎の門病院・肝臓センター) |
| 名越 澄子(埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科) 調 憲(群馬大学総合外科学講座) |
ウイルス性肝癌減少・非ウイルス性肝癌増加・肝障害軽度化・高齢化など、肝癌患者の背景には緩徐な変化が見られる。これらの時代の変化とともに、わが国の肝癌治療では、一般的ガイドラインから、より先進的で個別的な治療選択の方向にも向かっている。
経皮的治療・肝動脈化学塞栓療法は新たな手技・手段・薬剤の参入により、確実性や低侵襲化の検討がなされている。外科的にはさまざまなシミュレーションに加え、腹腔鏡下肝切除・肝移植が普及してきた。一方、新たに2種の分子標的薬が保険承認され、複数の薬剤の使い分け・使用順序も大きな関心がもたれている。これら有効性の高い抗がん剤に関して早期の導入を考慮するなどアルゴリズム運用の変化も見逃せない。わが国で先進的な精密放射線照射・強力粒子線治療は肝癌症例の背景の変化からも治療症例が増加している。
このようなわが国の実態を踏まえ、「現状と今後の展開」としての肝癌治療について活発な議論を期待したい。
シンポジウム3
| 座長: | 加藤 淳二(札幌医科大学医学部腫瘍内科学講座) |
| 神田 達郎(日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野) |
シンポジウム4
| 座長: | 吉田 寛(日本医科大学消化器外科) |
| 松岡 俊一(日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野) |
我が国にはおおよそ30人に一人が慢性肝炎に罹患していると言われている。慢性肝炎は年月とともに線維化が進行し、肝臓は硬変化して門脈末梢循環不全を来し、門脈圧亢進症を発症する。その代表的な合併症に消化管静脈瘤、異所性静脈瘤、難治性胸腹水、シャント性肝性脳症が挙げられ、これらに対する治療は目覚ましく進歩を遂げている。内視鏡治療としてEVL・EISなどが確立しており、特にIVR治療であるPSE・B-RTO・PTO・TIPS、また腹腔鏡下脾摘術・Hassab手術といった外科的治療は他国と比べ盛んに行われている。
門亢症の薬物治療はトルバプタンやリファキシミンが登場し現在浸透してきている。当シンポジウムでは門亢症の病態に関する臨床的な知見とともに、病態学、血行動態に基づいた内視鏡・IVR・外科治療について各施設独自の工夫などについて活発な討議を期待したい。更に新しいCART、腹腔-大静脈シャントの現状や門脈血栓症の特殊治療の臨床的知見についても発表頂きたい。
シンポジウム5
| 座長: | 稲垣 豊(東海大学医学部再生医療科学) |
| 榎本 信幸(山梨大学医学部第一内科) |
シンポジウム6
| 座長: | 加藤 昌彦(椙山女学園大学生活科学部管理栄養学科) |
| 上野 義之(山形大学医学部内科学第二講座(消化器内科学) |
シンポジウム7
| 座長: | 山本 雅一(東京女子医科大学消化器・一般外科) |
| 坂元 亨宇(慶應義塾大学医学部病理学教室) 加藤 直也(千葉大学大学院医学研究院消化器内科学) |
シンポジウム8
| 座長: | 泉 並木 (武蔵野赤十字病院消化器科) |
| 小川 眞広(日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野) |
シンポジウム9
| 座長: | 今関 文夫(千葉大学総合安全衛生管理機構) |
| 脇田 隆字(国立感染症研究所) 坂本 直哉(北海道大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野) |
ウイルス肝炎の克服・撲滅に向けた基礎、臨床研究は着実に進展してきた。
C型肝炎ウイルスに対しては、DAAの登場により大多数の症例でウイルス排除を達成することが可能となった一方で、高度薬剤耐性ウイルス、HBV再活性化、SVR後の肝組織・微小環境、免疫応答、糖脂質代謝等の変化など、それらの機序や肝発癌、生命予後に与える影響などを明らかにしなければならない。
B型肝炎ウイルスも核酸アナログ薬などにより肝炎の鎮静化と進展抑止が可能となった一方で、肝発癌抑止効果は不十分であり、ウイルス完全排除を目指した、種々のウイルス感染ライフサイクルを標的とした新規クラス薬剤、治療法の開発が進んでいる。
A型およびE型肝炎ウイルスについては年代別感染感受性や地域性などを正しく理解するとともに、E型肝炎の臓器移植患者などにおける慢性感染化に注意が必要である。
以上のごとく、ウイルス肝炎には解決すべき諸問題が山積している。本シンポジウムでは、これまでのウイルス肝炎領域の最新知見を明らかにして、今後必要な基礎・臨床研究の方向性について議論したい。
シンポジウム10
| 座長: | 滝川 一(帝京大学医療技術学部) |
| 松﨑 靖司(東京医科大学茨城医療センター) |
パネルディスカッション
| 座長: | 橋本 悦子(西武鉄道健康支援センター) |
| 大平 弘正(福島県立医科大学医学部消化器内科学講座) 田中 篤(帝京大学医学部内科学講座) |
ワークショップ1
| 座長: | 考藤 達哉(国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター) |
| 森屋 恭爾(東京大学大学院医学系研究科感染制御学) 寺井 崇二(新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野) |
ワークショップ2
| 座長: | 持田 智(埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科) |
| 徳重 克年(東京女子医科大学消化器内科) 四柳 宏(東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野) |
特別企画
| 司会: | 杉谷 雅彦(日本大学医学部病態病理学系形態機能病理学分野) |
| 中島 淳(横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病教室) 松本 直樹(日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野) |
【一般演題】
| 1 | B型肝炎 | 18 | 肝腫瘍(その他) |
| 2 | C型肝炎 | 19 | 嚢胞性肝疾患 |
| 3 | ウイルス性肝炎(B, Cを除く) | 20 | 肝移植後肝炎 |
| 4 | 非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD / NASH) |
21 | 肝移植 |
| 5 | 自己免疫性肝炎(AIH) | 22 | 手術・手技 |
| 6 | 原発性胆汁性胆管炎(PBC) | 23 | 肝線維化 |
| 7 | 原発性硬化性胆管炎(PSC) | 24 | 肝分化・肝再生・幹細胞 |
| 8 | 代謝性 / 先天性肝疾患・小児肝疾患 | 25 | 肝細胞・肝非実質細胞 |
| 9 | アルコール性肝障害 | 26 | 胆汁酸・胆汁うっ滞 |
| 10 | 薬物性肝障害 | 27 | 細胞死・アポトーシス・オートファジー |
| 11 | 肝硬変・慢性肝不全・肝性脳症 | 28 | バイオマーカー |
| 12 | 門脈圧亢進症・食道胃静脈瘤 | 29 | 臓器相関 |
| 13 | 急性肝炎 | 30 | 腸内細菌 |
| 14 | 劇症肝炎・急性肝不全 | 31 | 行政・地域医療 |
| 15 | 肝細胞癌 | 32 | 検診 |
| 16 | 肝内胆管癌 | 33 | その他 |
| 17 | 転移性肝癌 |
若手セッションへ応募の方は14番を選んでください。
| 1 | 形態・機能 | 8 | 診断 |
| 2 | 発症機序・病態 | 9 | 画像診断 |
| 3 | 遺伝子学・分子生物学 | 10 | 治療・予後 |
| 4 | 病理 | 11 | 基礎 |
| 5 | 免疫 | 12 | 臨床 |
| 6 | 疫学 | 13 | その他 |
| 7 | 予防 | 14 | 若手セッション |
特別企画
| コーディネーター: | 鈴木 義之(虎の門病院肝臓内科) |
| 海老沼浩利(国際医療福祉大学医学部) 山本 敏樹(日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野) |
登録文字数制限
演題名……全角70文字
抄録本文……全角1060文字
総文字数(著者名・所属・演題名・抄録本文の合計)……全角1200文字
演題の受領通知
ご入力いただきましたメールアドレス宛に「登録完了確認メール」が自動配信されますので演題登録の受領通知と致します。必ず確認メールがお手元に届いたことを確認して下さい。(通常, ご登録後5〜10分以内に送信されます。)セキュリティー保護のため, 事後のパスワードと登録番号の問い合わせへの応答は不可能ですので発行された登録番号とパスワードは必ずお書き留め下さい。1日経過しても登録完了確認メールがお手元に届かない場合は, 登録受付が完了していない可能性が高いので, 登録済み演題の修正・削除リンクボタンより正しく登録が完了しているかご確認下さい。
演題の採否通知
演題の採否, 発表時間, 発表形式は会長にご一任願います。
演題の採否通知は, 演題登録の際に各自入力された筆頭者のE-mailにお送りいたします。
E-mail アドレスは正確に入力をお願い致します。
入力文字について
「丸数字」「ローマ数字」は使用できません。英字の組み合わせで II, VI, XI のように入力して下さい。 シンボル (symbol) 書体半角 (1バイト文字)のα β γ 等を使用するとabcなどに自動変換されてしまいますので使わないようにして下さい。必ず全角(2バイト文字)のαβγを利用して下さい。 半角カタカナは使用できません。カタカナは全角で, 英字および数字は半角で記入して下さい。 タイトルおよび抄録本文で上付き文字, 下付き文字, 斜め (イタリック)文字, 太文字, 改行, アンダーラインを使うときに用いる <SUP></SUP>,<SUB></SUB>,<I></I>,<B></B>,<BR>,<U></U>の記号はすべて半角文字(1バイト文字)を使用して下英文や数字を入力する際, O (アルファベット)と0(数字)や, l (アルファベットL小文字)と1(数字), あるいはX (アルファベット)と×(かける)などきちんと区別して下さい。 音引き「ー」とダッシュ「―」, マイナス「-」とハイフン「-」などの使い分けをして下さい。 英文入力の際にひとつの単語をハイフン (-)で切ることは行わないで下さい。
その他
オンライン演題登録につきまして不明な点, 疑問等がございましたら下記のページをご覧下さい。
オンライン演題登録システムFAQ (一般利用者用)
http://www.umin.ac.jp/endai/userfaq.htm
演題登録画面へ
【主題演題・特別企画 症例に学ぶ】
| 【暗号通信】 | ||
 |
 |
|
| 【平文通信】 | ||
 |
 |
|
【一般演題・特別企画 若手セッション】
| 【暗号通信】 | ||
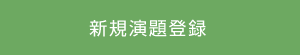 |
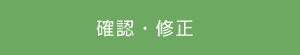 |
|
| 【平文通信】 | ||
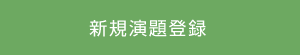 |
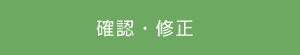 |
|
演題登録に関する問い合わせ先
第42回日本肝臓学会東部会運営事務局
(株)勁草書房 コミュニケーション事業部内
〒112-0005 東京都文京区水道2-1-1
Tel: 03-3814-7112 Fax: 03-3814-6904
E-mail: jsh42@keiso-comm.com










